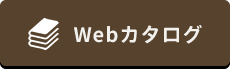理事長コラム~今月のひとこと~
バックナンバー
たかが服装
2024-12-18
30年以上前の話になりますが、『一緒がいいならなぜ分けた―特殊学級の中から』(現代書館)の著者北村小夜さんからつぎのような話を聞いたことがあります。
北村さんは、それまで勤めていた中学校の普通級から、当時特殊学級と呼ばれていた支援級に辞令で赴任します。その日に、生徒から放たれた言葉が忘れられないと言います。一つは、「先生も落第してきたんか」。もう一つは、「先生、ぼくらは汚いんか」と。
「落第」ということばには、支援級が置かれている、さらに言えば障害児者が置かれている(あるいは教員間の)差別・選別構造が端的に現われています。「一緒がいいならなぜ分けた」という有名なことばは、そういう排除される生徒たちの側から放たれたことばです。そして分けられたところから、つまり排除されたところから何を訴えていくのか、何をつくっていくのかということが、当時の支援級、養護学校には問われていました。「養護学校必要悪論」とも言い換えられます。結論だけを言えば、その延長にくれんどの仕事もあると考えています。
もう一つの「汚い」ということばは、もっと具体的で直接的です。当時の支援級での教員の服装のスタンダードは、ジャージでした。普通級の教員のスタンダードはスーツなのに、「ぼくらの先生は、なぜ1日目からジャージなのか。ジャージは作業や運動をするときに着るもの。ぼくらはそういう対象なのか」という告発であり、問いかけでした。そう聞いた北村先生は、その翌日から一張羅であるスーツを着て行ったと言います。
くれんどで「ジャージ不可」としたのは、このような考え方からです。ジャージそのものを否定しているわけではありません。くれんどの当事者からも「外出(移動支援)のときなどのジャージは止めてほしい。自分たちは介助される対象なんだと突きつけられているようで悲しい」と言われたことがあります。
くれんどで、食堂やパン屋などの接客以外でフォーマルな服やエプロンを身に着けないのはこんな理由からです。
その一方で、服装というときにもう一つ考えないといけないことがあります。それは、地域社会から現実にどう見られているのかという視点です。私たちが伴走している相手は、制度上からも社会的にも依然として差別を受けている人たちです。現実に「異形の存在」として社会的スティグマを背負わされている人たちです。そういう人たちと一緒にたとえば外出するのです。「枠」を超えていると見られれば(その枠は認知度や置かれている立場、あるいは状況によっても変わってくるのかも知れませんが)、場合によっては、社会の偏見、バイアスをさらに上塗りするということになりかねません。
非常に難しいことですが、服装・身だしなみは時代と社会の制約の中にあります。「たかが服装、されど服装」です。くれんどでも現在、あらためてその議論を始めたところです。
北村さんは、それまで勤めていた中学校の普通級から、当時特殊学級と呼ばれていた支援級に辞令で赴任します。その日に、生徒から放たれた言葉が忘れられないと言います。一つは、「先生も落第してきたんか」。もう一つは、「先生、ぼくらは汚いんか」と。
「落第」ということばには、支援級が置かれている、さらに言えば障害児者が置かれている(あるいは教員間の)差別・選別構造が端的に現われています。「一緒がいいならなぜ分けた」という有名なことばは、そういう排除される生徒たちの側から放たれたことばです。そして分けられたところから、つまり排除されたところから何を訴えていくのか、何をつくっていくのかということが、当時の支援級、養護学校には問われていました。「養護学校必要悪論」とも言い換えられます。結論だけを言えば、その延長にくれんどの仕事もあると考えています。
もう一つの「汚い」ということばは、もっと具体的で直接的です。当時の支援級での教員の服装のスタンダードは、ジャージでした。普通級の教員のスタンダードはスーツなのに、「ぼくらの先生は、なぜ1日目からジャージなのか。ジャージは作業や運動をするときに着るもの。ぼくらはそういう対象なのか」という告発であり、問いかけでした。そう聞いた北村先生は、その翌日から一張羅であるスーツを着て行ったと言います。
くれんどで「ジャージ不可」としたのは、このような考え方からです。ジャージそのものを否定しているわけではありません。くれんどの当事者からも「外出(移動支援)のときなどのジャージは止めてほしい。自分たちは介助される対象なんだと突きつけられているようで悲しい」と言われたことがあります。
くれんどで、食堂やパン屋などの接客以外でフォーマルな服やエプロンを身に着けないのはこんな理由からです。
その一方で、服装というときにもう一つ考えないといけないことがあります。それは、地域社会から現実にどう見られているのかという視点です。私たちが伴走している相手は、制度上からも社会的にも依然として差別を受けている人たちです。現実に「異形の存在」として社会的スティグマを背負わされている人たちです。そういう人たちと一緒にたとえば外出するのです。「枠」を超えていると見られれば(その枠は認知度や置かれている立場、あるいは状況によっても変わってくるのかも知れませんが)、場合によっては、社会の偏見、バイアスをさらに上塗りするということになりかねません。
非常に難しいことですが、服装・身だしなみは時代と社会の制約の中にあります。「たかが服装、されど服装」です。くれんどでも現在、あらためてその議論を始めたところです。