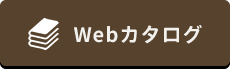理事長コラム~今月のひとこと~
バックナンバー
人材確保は人材定着から
2024-04-25
先日、行政関係者と人材確保策について懇談する機会があり、くれんどの人材確保、人材定着の現状についてふり返る機会を持つことが出来ました。
くれんどは、障害者の福祉就労モデルを地域につくることを目標の一つにしていますが、それ以前の内なる雇用はどうなっているのか。くれんどの職員のうち障害者は14.0%、高齢者(60歳以上)は30.4%(平均年齢50.4歳)です。障害者の法定雇用率は4月から2.5%に、さらに7月には2.7%になりますが、比べればくれんどははるかに高い数値となっています。障害者の一般就労を言うなら、まず隗より始めよということです。
また、高齢者が3割を超えていることは悲観的な数値とはとらえていません。むしろ評価されるべきことです。生物学者の小林武彦・東大教授は、『なぜヒトだけが老いるのか』という著書のなかで、進化の過程でヒトのシニアが果たした役割と意味を積極的に評価しています。障害者、シニアが地域就労のスタンダードモデルになれば、社会はもっとゆるくなるはずです。そしてこのノウハウがまた、他の社会的マイノリティ(引きこもり、刑余者、外国人等)の潜在労働力の活用、雇用へとつながり、結果として子どもの出生率の上昇にもつながると考えています。ちなみに、くれんどの全職員の平均年齢は50.1歳、常勤職員だけでいうと46.9歳です。
人口減少という縮小社会の出口をどこに求めるのか、それは必ずしも人口増加を目標にすることではありません。くれんどは福祉を通して、障害者や高齢者を始めとする社会的マイノリティの、セーフティネットと出番という一石二鳥の地域づくりをめざしています。障害者は「社会のお荷物」などではないことを、まず法人雇用から証明しようとしています。
そして雇用の次に大切なことは、人材の定着です。数値的には、くれんどの常勤率は61%70人、離職率は5.5%4人(新採用者は7人中1人)です。所詮相対的な比較ではありますが、くれんどの離職率がなぜ低いのか、それは、当事者活動を始めとする当事者や家族の置かれている現実が基盤に据わり、研修や諸会議を通してのチームワークが機能し、置かれた環境や制度についても情報共有をはかる体制が総体として機能しているからだと思っています。
この4月、くれんどには2名のメンバーと6名の新採用者を新たに迎えました。どんな風がふくのか楽しみです。
くれんどは、障害者の福祉就労モデルを地域につくることを目標の一つにしていますが、それ以前の内なる雇用はどうなっているのか。くれんどの職員のうち障害者は14.0%、高齢者(60歳以上)は30.4%(平均年齢50.4歳)です。障害者の法定雇用率は4月から2.5%に、さらに7月には2.7%になりますが、比べればくれんどははるかに高い数値となっています。障害者の一般就労を言うなら、まず隗より始めよということです。
また、高齢者が3割を超えていることは悲観的な数値とはとらえていません。むしろ評価されるべきことです。生物学者の小林武彦・東大教授は、『なぜヒトだけが老いるのか』という著書のなかで、進化の過程でヒトのシニアが果たした役割と意味を積極的に評価しています。障害者、シニアが地域就労のスタンダードモデルになれば、社会はもっとゆるくなるはずです。そしてこのノウハウがまた、他の社会的マイノリティ(引きこもり、刑余者、外国人等)の潜在労働力の活用、雇用へとつながり、結果として子どもの出生率の上昇にもつながると考えています。ちなみに、くれんどの全職員の平均年齢は50.1歳、常勤職員だけでいうと46.9歳です。
人口減少という縮小社会の出口をどこに求めるのか、それは必ずしも人口増加を目標にすることではありません。くれんどは福祉を通して、障害者や高齢者を始めとする社会的マイノリティの、セーフティネットと出番という一石二鳥の地域づくりをめざしています。障害者は「社会のお荷物」などではないことを、まず法人雇用から証明しようとしています。
そして雇用の次に大切なことは、人材の定着です。数値的には、くれんどの常勤率は61%70人、離職率は5.5%4人(新採用者は7人中1人)です。所詮相対的な比較ではありますが、くれんどの離職率がなぜ低いのか、それは、当事者活動を始めとする当事者や家族の置かれている現実が基盤に据わり、研修や諸会議を通してのチームワークが機能し、置かれた環境や制度についても情報共有をはかる体制が総体として機能しているからだと思っています。
この4月、くれんどには2名のメンバーと6名の新採用者を新たに迎えました。どんな風がふくのか楽しみです。